コラム記事
再建築不可物件とは?売却・対処のポイントを解説
公開日 2025年7月22日
最終更新日 2025年10月30日
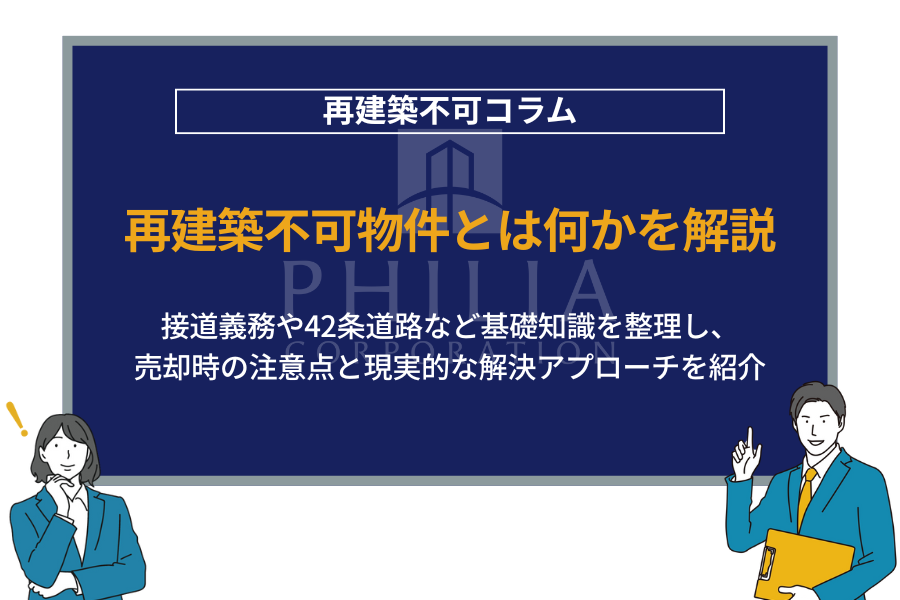
目次
はじめに:再建築不可と言われて不安なあなたへ
「親から相続した古い家が“再建築不可”だと言われたけれど、どうしたらいいの?」―このように戸惑い、不安な気持ちでこのページをご覧になっているかもしれません。建て替えができない物件だなんて、想像もしなかったでしょう。まして専門知識もない中で、「売ることも難しいのでは?」と焦ってしまうのも無理はありません。
ご安心ください。実は再建築不可物件の問題はあなただけの悩みではありません。都市部では東京都で21戸に1戸、神奈川県で18戸に1戸が再建築不可物件とも言われ、思いのほか身近に存在しているのです。本記事では、そんな再建築不可物件について初心者にもわかるよう丁寧に解説し、適切な対処法をご提案します。不安な気持ちに寄り添いながら進めていきますので、肩の力を抜いて読み進めてみてください。
再建築不可物件とは?その定義と背景
まずは「再建築不可物件」とは何かを押さえておきましょう。再建築不可物件とは、現在建っている建物を取り壊した後に新しく建物を建てることが法律上できない物件のことです。簡単に言えば、「解体後に再び建築できない土地・建物」を指します。
ではなぜ再建築ができないのでしょうか?主な理由は建築基準法の要件を満たしていないためです。建物を建て替える際には、現在の法律に従って建築確認申請を行い、許可を得る必要があります。しかし再建築不可物件は法律上の条件を満たさないため建築許可が下りず、新築はおろか大規模な増改築もできません。たとえば古い家屋をうっかり更地にしてしまうと、二度と住宅を建てられないまま土地だけが残ってしまうので注意が必要です。
再建築不可物件が生まれる主な原因
再建築不可物件が発生する背景には、いくつかの典型的な原因があります。ここでは代表的なケースを見てみましょう。
接道義務を満たしていない
現行の建築基準法第43条では、建物の敷地は幅員4メートル以上の道路(地域によっては6メートル以上)に2メートル以上接していなければならないと定められています。この「接道義務」を満たさない土地では建築確認がおりないため、再建築不可となります。例えば、家の敷地がまったく公道に接していない「袋地(ふくろじ)」や、わずかに道路に接していても道路幅が4m未満の私道しかない場合、あるいは道路に接する間口が1mほどしかない旗竿地(はたざおち)のような場合です。こうした土地では新たに家を建てることができません。接道義務は1950年の建築基準法改正で新設されたルールで、狭い路地に家が密集して火災時に消防車が入れない等の事態を防ぐために定められました。古くからの住宅地には、この法律施行前に建てられた建物が多く残っており、今になって再建築不可物件となっているケースが多いのです。
市街化調整区域に所在する
都市計画で定められた市街化調整区域(開発を抑制するエリア)にある物件も、新築や増改築に厳しい制限があるため再建築が難しい場合があります。市街化調整区域内で戦後すぐに建てられた住宅などは、現在では原則として建て替えが認められません。ただし一定の条件を満たせば許可が下りるケースもありますが、手続きは非常にハードルが高く、多くの時間と費用を要します。
以上が代表的な原因ですが、この他にも古い長屋建て(連棟式)の一部で単独では再建築できないケースや、文化財指定等で勝手に改築できない建物なども広い意味で再建築不可に該当する場合があります。ただし多くは法律の接道要件が絡んでいるケースです。要するに、再建築不可物件とは「法律上、新築の許可が下りない物件」だと理解しておきましょう。
再建築不可物件のリスク・問題点
再建築不可物件を所有すると、普通の物件にはない様々なデメリットやリスクに直面します。ここでは主な問題点を整理してみます。
住宅ローンが利用できず資金計画が立てにくい
再建築不可物件は一般的に銀行からの評価が低く、買主が住宅ローンを組めない場合がほとんどです。そのため現金購入できる一部の限られた人しか買えず、結果として売却時に買い手探しが難航しがちです。また、自分で住み続けるにしても建て替えできない以上リフォームローンも利用しづらいのが現状です。
売却が難しく、価格も周辺相場より安い
再建築不可物件は市場ではいわゆる「訳あり物件」として敬遠される傾向にあります。買い手がつきにくい分、価格も通常の類似物件より大幅に低く評価されてしまいます。一般には、再建築不可物件の売却価格は周辺の再建築可物件の約5割~7割程度まで下がるともいわれます。築年数が古い物件が多いことも価格下落に拍車をかけます。資産価値が伸びにくいため、不動産としては不利な状況になりやすいのです。
老朽化しても建て直しできず、倒壊時も再建築不可
再建築不可物件では老朽化が進んでも全面的な建て替えができないため、手を入れるにも限界があります。耐震性に不安があっても、大規模な改修は建築確認が下りないため困難です。そのまま放置すれば建物の安全性は低下し続け、地震や火災で万一倒壊してしまっても新しく建て直すことはできません。さらに接道条件を満たしていない場所では消防車や救急車が入れず被害が拡大する恐れもあります。こうしたリスクを抱えながら維持していく必要がある点は、大きな不安材料と言えます。
維持管理や活用に手間とコストがかかる
建物が古く傷んできても建て替えできない以上、住み続けるなら都度修繕して延命するしかありません。シロアリ被害があっても基礎から全面的に作り直すことはできず、応急処置で凌ぐケースもあります。その割に借り手・買い手が付きにくいため、空き家のまま放置すれば管理費用や防犯対策の負担がかかります。また更地にして駐車場等に活用しようにも後述のとおり税負担が大きくなるため、安易に解体することも躊躇われる状況です。結果として持ち主にとっては「使うにも使えず、維持費ばかりかさむ」物件になりがちです。
更地にすると固定資産税が大幅増額する
古家を思い切って取り壊し、更地で活用しようと考える方もいるでしょう。しかし再建築不可物件の場合、更地にしてしまうと新築ができない上に税負担まで跳ね上がる点に注意が必要です。日本の税制では住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」により固定資産税・都市計画税が軽減されていますが、建物を取り壊すとその特例が受けられなくなります。具体的には、小規模住宅用地にかかる固定資産税は土地評価額の1/6に軽減されていますが、更地になるとこれが解除され税額が最大で6倍になるケースもあります。再建築不可物件を更地にすることは、文字通り「使えない土地」を抱えたまま税金だけ大きく増えてしまう可能性があるのです。
以上のように、再建築不可物件には経済面・安全面で多くのリスクやデメリットがあります。相続した方にとっては「持っているだけで負担が増す不動産」になりかねません。もちろん物件によって事情は様々ですが、こうした問題点を踏まえた上で次に述べる対処法を検討していくことが大切です。
再建築不可物件への対処法:売却・活用の具体策
それでは、再建築不可物件を抱えてしまった場合にどのような対処法があるかを見ていきましょう。「売る」か「活用する」か、大きく分けて二つの方向性があります。それぞれの具体策を順に解説します。
1.再建築不可物件を売却する方法
できるだけ早く手放してしまいたいという場合、売却を検討するのが現実的な選択肢です。ただし前述のように通常の不動産売買より難易度が高いため、売却先や売却方法に工夫が必要です。主な売却方法としては次のようなものがあります。
隣地の所有者に売却を打診する
再建築不可物件にとって一番身近な買い手候補は、お隣や近隣に住む方です。隣接地の所有者であれば、その土地を購入して自分の土地と一体利用することで接道条件を満たし、将来的に再建築可能にできる可能性があります。また、駐車場や庭を広げたいという目的で買ってくれるケースもあります。近隣なら土地勘もあり、メリットを感じてもらえれば意外とスムーズに話が進むこともあります。ダメ元でも一度声をかけてみる価値はあるでしょう。
不動産仲介会社を通じて一般に売却する
通常の不動産市場に流通させて広く買い手を探す方法です。不動産仲介会社に依頼して広告を出してもらい、購入希望者を募ります。デメリットはやはり買い手が見つかりにくく時間がかかる点です。価格を周辺相場より相当安く設定すれば投資目的の購入希望者が現れる可能性もありますが、その場合ご自身が受け取れる金額は低くなってしまいます。また仲介では成約までに時間が読めず、長期間売れ残るリスクもあります。早く確実に現金化したい場合には不向きかもしれません。
専門の不動産買取業者に直接買い取ってもらう
最近増えているのが、再建築不可物件の買取を専門に扱う業者に売却する方法です。こうした専門業者であれば、再建築不可物件の価値や問題点を踏まえた上で活用策を持っているため、そのままの状態でも買い取ってもらえるケースが多いです。仲介と違って業者が直接買主となるため、買い手探しの期間が必要なくスピーディーに売却できるのが大きな利点です。また後述する事例のように、家具や荷物が残ったままでもまとめて引き取ってくれる業者もあります。価格は業者の提示額次第ですが、「手間・時間をかけず確実に処分したい」なら検討する価値は高いでしょう。
以上の方法を組み合わせたり、まずは隣地に声をかけてダメなら買取業者に…と順番に試したりと、状況に応じた進め方が考えられます。ポイントは、再建築不可物件でも売却自体は可能だということです。「売れない不動産」とあきらめる必要はありません。
2.再建築不可物件を活用する方法
一方で、「思い出の家だからすぐに手放すのも忍びない」「条件が好転するまで所有し続けたい」という場合は、現在の状態でなんとか活用する道を探ることになります。再建築不可物件は新築が建てられないだけで、今ある建物を使うこと自体は違法ではありません。以下のような活用策があります。
居住用にリフォーム・修繕して使い続ける
建て替えはできませんが、法律の範囲内でリフォームや修繕をして住み続けることは可能です。例えば水回り設備の交換や内装の改装、耐震補強工事など、建築確認申請が不要な規模のリフォームであれば問題ありません。ただし増築や構造に関わる大規模リフォームは不可なので、あくまで現状の枠を大きく変えない範囲にとどまります。築年数次第では快適性に限界がありますが、工夫次第であと数十年は使えるケースもあります。費用対効果や安全性を見極めながら検討しましょう。
賃貸やシェアハウスとして人に貸す
自分で住まないのであれば、他人に貸し出して家賃収入を得る方法もあります。築古でも立地が良ければ、リフォームして安価な賃貸(一戸建て貸家やシェアハウス)にすれば借り手が見つかる可能性があります。実際、「格安でも良いから都内に住みたい」という需要や、再建築不可を承知で購入する投資家も一定数存在します。ただし老朽化した建物を貸す場合は借主の安全確保や万一の損傷トラブルなどにも留意が必要です。賃貸に出す際は、不動産会社に管理を委託するなどリスクヘッジもしましょう。
駐車場・資材置場など土地のみ活用
建物を取り壊すと再建築はできませんが、更地にして土地自体を活用することは可能です。例えば駐車場(車が入れる立地なら)やトランクルーム用地、家庭菜園・資材置場などに利用できます。ただし前述の通り更地にすると固定資産税が跳ね上がる点には注意が必要です。収益性と維持費のバランスをよく考え、収入が見込める活用でなければおすすめできません。特に再建築不可物件は車両が入れない立地も多く、駐車場としての利用が成り立たないケースもあります。土地活用するならその点も含めた計画が必要です。
再建築不可を解消する努力をする
これは活用というより根本解決策ですが、条件次第では再建築不可の状態を解消してしまうことも検討に値します。具体的には、隣地を一部買い足して敷地を道路に2m以上接するようにする、あるいは行政に働きかけて私道を「位置指定道路」として認可してもらう、さらには建築基準法第43条ただし書きの許可(いわゆる43条但し書き道路の建築許可)を取得する、といった方法です。ただしこれらはいずれもハードルが高く専門知識と費用を要する手段です。隣地を購入するにはまとまった資金が必要ですし、行政手続きも専門家(建築士や行政書士など)のサポートが不可欠です。将来的にその土地にどうしても新築を建てたい事情がある場合を除き、相続者の方が無理に取り組むケースは少ないでしょう。とはいえ「隣の土地を譲ってもらえる話がある」「自治体が再開発計画で道路整備を検討している」といった状況なら、一度専門家に相談してみる価値はあります。
以上のように、活用策はいくつかありますがどれも一長一短で簡単ではないのが現実です。特に相続で引き継いだ50代前後の方にとって、老朽住宅の維持管理や交渉・手続きを一人で背負うのは大きな負担でしょう。無理に活用しようとして時間と費用をかけても、結局状況が改善しないまま疲弊してしまうケースもあります。
困ったときは専門家への相談を検討しましょう
再建築不可物件の対処に悩んだら、早めに不動産の専門家へ相談することも重要です。とりわけ再建築不可物件の扱いに慣れた業者であれば、有効な解決策を提案してくれる可能性が高いです。「売るに売れない」と思い込んでいた物件でも、専門業者なら法的な問題を解消して運用・再販するノウハウがあるため、そのまま買い取ってもらえる場合があります。一人で抱え込まず、プロの知見を借りることで道が開けることも多いのです。
フィリアコーポレーション(当社)もまさに再建築不可物件などの特殊な不動産に特化した専門業者の一つです。次章では、フィリアコーポレーションが実際に手がけた事例をもとに、再建築不可物件の問題解決の流れを見てみましょう。ご自身の状況に置き換えて、具体的なイメージを持っていただければ幸いです。
【事例】「再建築不可の空き家」を専門業者に買い取ってもらい解決したケース(板橋区・築50年)
ここでは、実際にフィリアコーポレーションが対応した相談をモデルにしたリアルな事例をご紹介します。
〈ご相談者〉
新宿区在住50代女性(会社員)。数年前に亡くなった母親の実家(板橋区内の一戸建て)を相続。築50年以上経つ木造住宅で、現在は誰も住んでおらず空き家になっている。
〈物件の状況〉
玄関前の道路が幅2メートル程度の狭い私道で車両の進入不可。敷地は路地の奥まった所にあり、建築基準法上の道路に2m以上接していないため再建築不可と判明。建物は昭和40年代築で老朽化が進み、雨漏りや柱の腐食が見られる。近隣も同様に古い住宅が密集している地域。
〈相談時の状況・お悩み〉
ご相談者は母の家を将来的に建て直して自分たち家族で住むことも考えていたが、役所に相談したところ「この土地は再建築不可なので建て替えはできない」と告げられ愕然。リフォームしようにもあまりに古いため費用が読めず、空き家のまま放置すれば倒壊や近隣への迷惑も心配で不安を抱えていた。また自身は都心のマンション住まいで仕事も忙しく、実家の管理に頻繁に通うことも難しかった。地元の不動産会社に売却査定を依頼してみたものの、「再建築不可なので正直買い手がつかないでしょう」と渋い反応で、自分ではどうしようもないと途方に暮れていた。
〈フィリアコーポレーションへの相談~解決まで〉
そんな中、ご相談者はインターネットで「再建築不可物件の買取実績が豊富」というフィリアコーポレーションを知り、思い切って問い合わせをいただきました。早速担当者が現地を調査したところ、幸い建物の基礎はしっかりしており現状のままでも十分買い取れると判断。ご相談者が仕事でお忙しいことも配慮し、電話とメールで迅速にやり取りを行いました。
スピード査定・即日お見積もり
内見したその日のうちに社内検討を行い、即日で買取可能額の概算を提示。「この金額でよろしければすぐにでも契約できます」とお伝えしました。再建築不可という特殊事情を考慮したうえでの価格でしたが、当初ご相談者が想像されていたよりも十分納得いただける金額でした。買い手探しが難航することを覚悟されていたため、「本当にこのまま買ってもらえるんですか?」と半信半疑でしたが、当社としても蓄積したノウハウで再販の見通しが立っていたため自信を持ってご提案しました。
契約手続きと引き渡し
ご提示額にご同意いただけたため、すぐに売買契約の準備に入りました。売主であるご相談者様は仲介手数料等の費用負担は一切なし。当社が直接買主となるため、仲介会社を挟まない分コストがかからないことをご説明しました。また、家の中に残ったままになっていた荷物や家具もすべて当社で撤去処分することをお約束しました。相続した実家には思い出の品も多く、処分の踏ん切りがつかないまま時間が経っていたそうですが、「必要なものだけ持ち出せば、あとはそのままで大丈夫です」と申し上げると肩の荷が下りたご様子でした。契約書の取り交わし自体はシンプルで、ご相談から約1週間後には売買契約を締結。その後、残っていたお荷物の搬出など最低限の準備を経て、1か月後には物件の引き渡し(決済)まで完了しました。
〈結果とご相談者の声〉
再建築不可物件という難しい不動産だったにもかかわらず、想定より早く安全に売却できたことで、ご相談者は大変安心されていました。特に「こちらでほとんど何もしなくても、家財道具も含めそのまま引き取ってもらえて本当に助かりました」と笑顔でお話しくださいました。また、「母の家を更地にして放置したら税金や管理で苦労するところだった。プロに任せて正解でした」というお言葉もいただいています。
フィリアコーポレーションでは、このように売主様の負担を極力軽減しながら再建築不可物件の買取を行っています。スピーディーな現金化はもちろん、契約後のトラブルを避けるため売主様の契約不適合責任も免除させていただいております。これは売却後に何か物件の不具合が見つかっても売主様に責任追及しないという取り決めで、一般の売買ではなかなか難しい条件です。当社にお任せいただければ、こうした面でも安心してお取引いただけます。
この事例は特殊なケースに思えるかもしれませんが、再建築不可物件に直面した相続者の方にとって決して他人事ではありません。同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門業者に相談するという選択肢も検討してみてください。
よくある質問(FAQ)
Q
再建築不可物件でもリフォームや増築はできますか?
Q
自分の物件が再建築不可かどうか素人でも調べられますか?
Q
「再建築不可物件は売れない」と聞きますが、本当に売却は難しいのでしょうか?
Q
再建築不可物件を将来的に再建築できるようにする方法はありますか?
以上のような法的・物理的手段で再建築可能に持ち込めるケースもゼロではありません。ただし素人が単独で進めるのは難しく、実現できても費用対効果に見合わないこともあります。現実的には「再建築不可のまま売却してしまい、別の再建築可能な物件を購入する」方がコストも時間も節約になる場合が多いです。専門家と相談し、無理のない範囲で検討することをおすすめします。
まとめ:再建築不可物件に振り回されないために
再建築不可物件について、その定義や背景からリスク、対処法まで一通り解説してきました。最後に要点を振り返ってみましょう。
再建築不可物件とは
建築基準法の接道義務などを満たさず、建物を取り壊した後に新築できない物件のこと。狭い路地に面した古い住宅などに多い。古家付きで売買され、取り壊すと二度と家が建てられない点に注意。
発生する理由
主に道路に2m以上接していないことが原因(幅員4m未満の道路しかない、袋小路になっている等)。1950年に法律が改正された際の新ルールで、それ以前から建っている建物が該当する場合が多い。他に市街化調整区域の厳しい制限下にあるケースなども。
抱えるリスク・問題点
建て替え不可による資産価値の低下(市場価格は周辺相場の半額程度になる例も)、住宅ローン利用不可、老朽化しても建築確認が下りないため大規模改修できない、安全性の不安(倒壊しても再建築不可)、更地にすると税金負担増などデメリット多数。普通の不動産に比べて出口(売却)戦略が限定され、放置すると管理費用や近隣トラブルのリスクも高まる
対処法・活用法
売却するか活用するかの二択。売却なら①隣地へ売却打診、②仲介で一般募集、③専門業者への直接買取という方法がある。専門業者ならそのまま買い取ってもらえるケースが多く、早期解決に向く。活用するなら①現状のままリフォームして住む(小規模改修のみ)、②賃貸に出す(安価なら借り手の可能性)、③更地にして駐車場等で活用といった策があるが、更地は税負担増に注意。④条件を整えて再建築可能にする(隣地購入や43条許可など)という根本解決も一応あるが、難易度が高い。
専門家への相談の重要性
再建築不可物件は素人判断で動かず、まずは実績ある専門家に相談すべき。特に買取業者なら法的問題をクリアして再生するノウハウがあるため、「再建築不可でも売れるところには売れる」という事実を知ってほしい。自分一人で抱え込まず、プロの力を借りることでリスクを最小限に解消できる。
以上のポイントを踏まえれば、再建築不可物件に対して取るべき行動が見えてくるはずです。大切なのは「放置しないこと」。不安だからとそのままにしておくと、時間の経過とともに物件の状態も悪化し、問題が大きくなってしまいます。今回の記事が、同じ悩みを持つあなたの背中を少しでも押し、行動を起こすきっかけになれば幸いです。
「再建築不可だから」と悲観的になる必要はありません。専門家の知恵や周囲の協力を得れば、きっと最善の解決策が見つかります。あなたの大切な財産を守るために、ぜひ前向きに対処法を検討してみてください。

越川直之【宅地建物取引士】【空き家相談士】
代表ブログへ
株式会社フィリアコーポレーション代表取締役の越川直之です。
当社は空き家や再建築不可物件、共有持分など、一般的に売却が難しい不動産の買取・再販を専門とする不動産会社です。
これまでに1000件以上の相談実績があり、複雑な権利関係や法的・物理的制約のある物件にも柔軟に対応してきました。
弊社ホームページでは現場経験に基づいた情報を発信しています。
当社は地域社会の再生や日本の空き家問題の解決にも取り組んでおり、不動産を通じた社会貢献を目指しています。
