コラム記事
長屋売却時のご近所トラブル注意報!共有部分と隣人への配慮
公開日 2025年9月6日
最終更新日 2025年10月30日
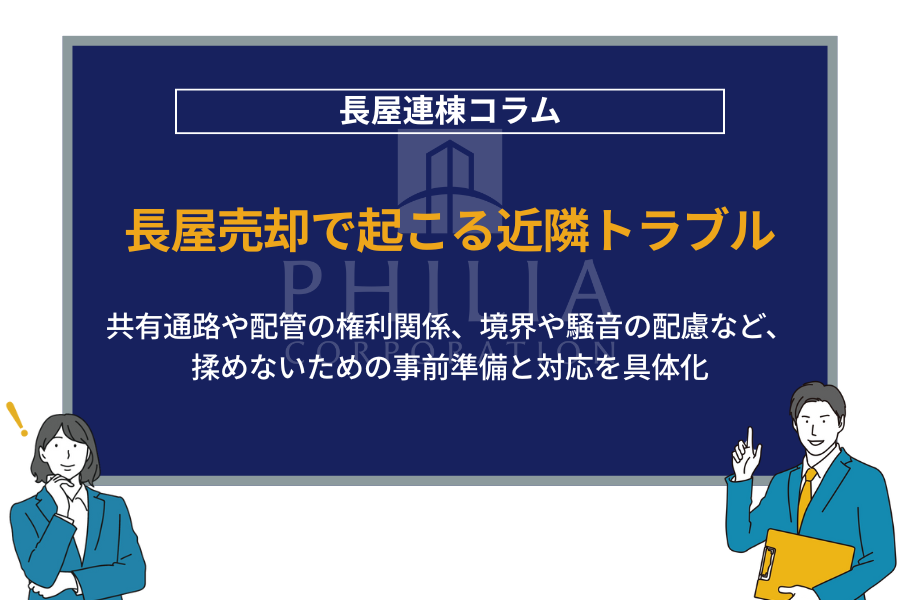
長屋の売却を考えたとき、ふと頭をよぎる隣人の顔。「売却の話をしたら、どう思われるだろうか…」その不安、痛いほどわかります。長屋の売却は、物件そのものより、隣人との関係が成功の鍵を握るといっても過言ではありません。この記事では、ご近所トラブルを避け、円満に売却を進めるための具体的な配慮と方法を、専門家の視点から詳しく解説します。
目次
そもそも長屋の「共有部分」とは?トラブルの火種となる3つの箇所
この章では、長屋に特有の「共有部分」について、特にトラブルの原因となりやすい3つの箇所を具体的に解説します。
- ① 建物の基本構造を支える「界壁・柱・基礎」
- ② 生活インフラを共有する「水道管・ガス管」
- ③ 見落としがちな「屋根・雨どい」
長屋の売却が一般的な戸建てと大きく異なるのは、隣家と建物を**「共有」**している点にあります。文字通り、壁や基礎、インフラなどを共有しているため、ご自身の判断だけでは解体や大規模なリフォームができません。この「共有部分」の存在こそが、隣人トラブルの根本的な原因となります。まずはどこが共有部分にあたるのかを正しく理解し、トラブルの火種を把握することから始めましょう。
① 建物の基本構造を支える「界壁・柱・基礎」
長屋の売却を考える上で、最も重要かつトラブルの根源となりやすいのが、隣家との境界にある壁、すなわち界壁(かいへき)です。この壁は、単なる間仕切りではありません。柱や基礎と同様に、建物全体の構造を支える極めて重要な共有部分なのです。
なぜなら、これらの構造部分は法的に一心同体と見なされ、建物の強度や安全性に直接関わるからです。そのため、たとえご自身の所有する敷地側であっても、勝手に解体したり、穴を開けたりすることは許されません。もし強行すれば、建物全体の耐震性が低下し、最悪の場合、隣家を倒壊の危険に晒すことになりかねません。
実際に、解体や大規模リフォームには隣人の同意が不可欠となるのは、この構造上の共有が最大の理由です。ご自身の財産でありながら、自由にならない部分がある。この大原則をまず認識することが、長屋売却の第一歩と言えるでしょう。
② 生活インフラを共有する「水道管・ガス管」
次に注意すべきは、壁や床下を通っている水道管やガス管といった生活インフラです。特に築年数の古い長屋では、隣家とこれらの配管を共有しているケースが少なくありません。建築当時に効率を優先し、一本の主管から各戸へ配管を枝分かれさせている設計が多いためです。
この構造が問題となりやすいのは、売却後のリフォーム時です。例えば、買主がキッチンの位置を変更したい場合、新たな給排水管の引き込みが必要になります。その工事のために隣家の敷地を掘削する必要が生じたり、配管の切り離し費用の負担をめぐって意見が対立したりと、トラブルに発展する可能性を秘めています。
私たちは、この目に見えないインフラの問題が原因で、売買契約が直前で白紙になったという苦い事例も見てきました。売却を検討する際は、事前に配管の状況を図面などで確認し、リスクを把握しておくことが重要です。
③ 見落としがちな「屋根・雨どい」
最後に、意外な落とし穴となるのが屋根や雨どいです。多くの長屋は、複数の住戸が一体となった大きな屋根で覆われており、雨どいも連続して設置されています。これらも当然、重要な共有部分となります。
屋根は建物全体を雨漏りから守り、雨どいは敷地全体からの排水を担うため、これらは一心同体です。例えば、ご自身の家側の屋根だけを新しい素材に葺き替えようとすると、隣家との接合部分に隙間が生まれ、かえって雨漏りのリスクを高めてしまうかもしれません。
実際に、片方の家の雨漏り修繕の費用負担をめぐって関係が悪化し、売却の話がまったく進まなくなったというご相談も受けたことがあります。売却前の点検では、つい建物の内部や壁に目が行きがちですが、屋根や雨どいの状態も隣家と共有する財産として認識しておくことが大切です。
\ 無料で安心!まずは査定から /
今すぐあなたの物件をチェック
長屋売却で隣人トラブルが起こりやすい3つのタイミング
共有部分の存在を理解したところで、次に、具体的にどのようなタイミングで隣人トラブルが発生しやすいのかを見ていきましょう。
- ①【売却前】解体・建て替えの「同意」を求める時
- ②【売却中】購入希望者の「内覧」の時
- ③【売却後】新所有者による「リフォーム・工事」の時
長屋の売却をめぐるトラブルは、売却の準備から売却後の未来まで、様々な段階で発生する可能性があります。特に注意すべきなのは、隣人への「協力」や「理解」が不可欠となるタイミングです。これから解説する3つのタイミングは、どれも売主様の配慮一つで、円満に進むか、関係が悪化するかの分かれ道となります。事前にリスクを把握し、慎重に行動することが求められます。
①【売却前】解体・建て替えの「同意」を求める時
長屋売却における最初の、そして最大の難関が、解体や建て替えの「同意」を隣人に求めるタイミングです。実際、私たちへのご相談で最も多いのが、この同意取得に関するお悩みと言っても過言ではありません。
隣人からすれば、これは何のメリットもない一方的な「お願い」です。ご自身の家の安全性が損なわれないか、工事の騒音はどの程度か、といった不安が先に立ちます。中には、同意を盾に承諾料(ハンコ代)を要求してくるケースも残念ながら存在します。
特に、普段お付き合いのない隣人に対して、このような重大な依頼をすることに強い心理的抵抗を感じる売主様は非常に多いです。このデリケートな交渉をどう切り出すかが、売却活動全体の行方を左右する最初の関門となるのです。
②【売却中】購入希望者の「内覧」の時
意外に思われるかもしれませんが、購入希望者が物件を見に来る「内覧」も、隣人トラブルの火種となり得ます。売主様にとっては重要な販売活動ですが、隣人からすれば、見知らぬ人が自宅の周りをうろつくことになり、プライバシーを侵害されているようで、あまり気持ちの良いものではありません。
特に、購入希望者が敷地の境界を越えて隣家の敷地に立ち入ってしまったり、内覧に来るたびに騒がしかったりすると、隣人の不満は少しずつ溜まっていきます。過去には、内覧に来た購入希望者が隣人に直接声をかけ、根掘り葉掘り質問したことで関係が悪化してしまった、という事例もありました。
売却活動が長期化すれば、それだけ隣人に与えるストレスも増えていきます。内覧を行う際には、事前に隣人へ一声かけておく、案内する不動産会社に隣人への配慮を徹底してもらう、といった気配りが、円満な売却のためには不可欠です。
③【売却後】新所有者による「リフォーム・工事」の時
「売却さえ済んでしまえば、もう安心」とは言い切れないのが長屋の難しいところです。トラブルは、あなたが所有者でなくなった後にも発生する可能性があります。それは、新しい所有者がリフォームや工事を始める時です。
もし、あなたが買主に対して共有部分に関するルールや、隣人への配慮の必要性を十分に説明していなかった場合、どうなるでしょうか。新しい所有者が隣人に無断で騒音の出る工事を始めれば、隣人の怒りの矛先は、新しい所有者だけでなく「そんな人に売ったあなた」にも向けられかねません。
これは、売主が負うべき「契約不適合責任」にも関わる重大な問題です。せっかく売却できたのに、何年も経ってから隣人からクレームの連絡が来る…そんな事態は絶対に避けたいはず。本当の意味で円満な売却とは、将来にわたる不安の種をすべて断ち切ることなのです。
\ 無料で安心!まずは査定から /
今すぐあなたの物件をチェック
【事例紹介】実際にあった!長屋売却をめぐる3つの隣人トラブル
これまでトラブルが起こりやすいタイミングを解説してきましたが、ここでは、私たちフィリアコーポレーションが実際に経験した、より生々しいトラブル事例をご紹介します。
- ケース1:解体同意と引き換えに、高額な承諾料を要求された(東京都世田谷区の事例)
- ケース2:売却後に「壁にひびが入った」と買主・隣人からクレームが…(神奈川県川崎市の事例)
- ケース3:隣地の越境を指摘され、売買代金の減額を求められた(埼玉県さいたま市大宮区の事例)
これらは決して他人事ではありません。長屋の売却では、法律や理論だけでは割り切れない、人間関係に起因する根深い問題が起こりがちです。ご自身の状況と照らし合わせながら、リアルなリスクを感じ取ってみてください。
ケース1:解体同意と引き換えに、高額な承諾料を要求された(東京都世田谷区の事例)
これは東京都世田谷区で、ご相続された長屋の売却をご検討されていたA様から受けたご相談です。買主は再建築を希望していたため、隣家からの解体同意が必須でした。A様が丁寧にお願いに伺ったところ、当初は曖昧な返事だった隣人が、後日になって「承諾料として300万円を支払ってほしい」と要求してきたのです。
お話をお伺いすると、隣人の息子様が入れ知恵をしていたようでした。「解体には協力するが、それ相応の迷惑料、協力費をいただくのが当然だ」という主張です。A様は買主から提示された売却価格から、とても支払える金額ではなく、交渉は完全に暗礁に乗り上げてしまいました。このように、法的な権利を盾に、高額な金銭を要求されるケースは後を絶ちません。
ケース2:売却後に「壁にひびが入った」と買主・隣人からクレームが…(神奈川県川崎市の事例)
これは、神奈川県川崎市で長屋の売却を終えたB様が、数ヶ月後に直面したトラブルです。B様は一般的な不動産仲介で無事に売却を終え、ほっとしていました。しかし、ある日、買主から「リフォーム工事を始めたら、隣の家との間の壁にひびが入った。これは売主の責任ではないか」と連絡が入ったのです。
さらに、隣人からも「あなたの家を売ったせいで、うちの壁に被害が出た」とクレームが来てしまい、B様は買主と隣人の双方から責められる立場に追い込まれました。これは、売主が引き渡し後も一定期間負わなければならない「契約不適合責任」が問われた典型的なケースです。
最終的に、専門家による調査で因果関係がないと証明できましたが、B様はその解決のために多大な時間と精神的な負担を強いられました。売却後も安心できないリスクが、長屋取引には潜んでいます。
ケース3:隣地の越境を指摘され、売買代金の減額を求められた(埼玉県さいたま市大宮区の事例)
これは、埼玉県さいたま市大宮区の長屋を売却しようとしたC様のケースです。買主も見つかり、契約直前という段階で、買主側が念のため敷地の測量を行いました。すると、C様の家の屋根の軒先が、数センチほど隣の敷地にはみ出している「越境」の状態であることが発覚したのです。
この事実を知った隣人は態度を硬化。「今まで黙っていたが、越境を解消しない限り、売却に必要な書類には一切判を押さない」と主張し始めました。板挟みになった買主は、将来のトラブルを懸念し、C様に対して「越境問題のリスク分として、売買代金を減額してほしい」と要求。
C様は売却を断念するわけにもいかず、最終的にその要求を飲むしかありませんでした。ご自身が全く認識していなかった問題で、手にするはずだった金額が目減りしてしまったのです。境界が曖昧な古い長屋には、こうした金銭的なリスクも潜んでいます。
\ 無料で安心!まずは査定から /
今すぐあなたの物件をチェック
ご近所と揉めずに長屋を円満に売却する3つのステップ
ここまで読んで、長屋売却の難しさに不安を感じてしまったかもしれません。しかし、ご安心ください。次に、これらのトラブルを未然に防ぎ、円満に売却を進めるための具体的なステップをご紹介します。
- ステップ1:まずは共有部分の範囲と権利関係を正確に把握する
- ステップ2:売却の意思を丁寧に伝え、良好な関係を築く
- ステップ3:それでも不安なら「専門の買取業者」に丸ごと任せる
恐ろしい事例を見てきましたが、これらはすべて「準備不足」と「コミュニケーション不足」が根底にあります。逆に言えば、正しい手順を踏むことで、トラブルのリスクは大幅に軽減できるのです。ここからの3つのステップは、ご自身で売却を進める上での、いわば「お守り」のようなもの。一つずつ着実に実行していきましょう。
ステップ1:まずは共有部分の範囲と権利関係を正確に把握する
隣人との交渉を始める前に、必ずやるべきことがあります。それは、ご自身の長屋の「現状」を客観的な事実として正確に把握することです。感情や思い込みで話を進めるのは、トラブルの元凶となります。
具体的には、法務局で登記簿謄本を取得したり、建築時の図面や境界に関する覚書がないか探したりすることから始めましょう。これらの資料をもとに、どこまでが共有部分で、法的にどのような権利・義務があるのかを明確にします。例えば、壁は構造を共有する「界壁」なのか、単に接しているだけなのかで、話の進め方は全く異なります。
この事実確認を怠ると、いざ交渉の場で隣人から想定外の指摘をされた際に、しどろもどろになってしまい、信頼を失いかねません。まずは敵(問題)を知ることから。これが円満解決に向けたすべての土台となります。
ステップ2:売却の意思を丁寧に伝え、良好な関係を築く
ご自身の長屋の状況を把握できたら、次はいよいよ隣人へ売却の意思を伝えるステップです。ここでの鉄則は「誠実さ」と「丁寧さ」に尽きます。相手も人間です。一方的にこちらの要求を突きつけるのではなく、まずは相手の立場を尊重する姿勢を見せることが、良好な関係を築く鍵となります。
「実は、この家を売却しようと考えておりまして、ご迷惑をおかけしないように進めたいので、一度ご挨拶に伺いました」といったように、命令や要求ではなく、あくまで「相談」や「報告」という形で切り出すのが良いでしょう。その際には、手土産の一つでも持参し、話し合いの時間を取ってもらったことへの感謝を伝えることも大切です。
焦らず、感情的にならず、一人の人間として真摯に向き合うこと。この丁寧なコミュニケーションが、後のトラブルを防ぐ最も有効な「防波堤」となってくれるはずです。
ステップ3:それでも不安なら「専門の買取業者」に丸ごと任せる
ステップ1と2を解説しましたが、「それでも、やっぱり隣人と話すのは気が重い」「すでにトラブルになりかけている」という方もいらっしゃるでしょう。その場合は、無理にご自身で進めようとせず、専門家を頼るのが賢明です。その最終手段が、私たちのような**「専門の買取業者」**に丸ごと売却を任せる、という選択肢です。
専門の買取業者は、トラブルや問題を抱えた不動産を「現状のまま」買い取ります。つまり、これまで解説してきたような隣人との交渉、境界線の確定、売却後の責任(契約不適合責任)といった、売主様を悩ませるすべての事柄を、私たちが引き継ぐのです。
あなたは、面倒な交渉や手続きから一切解放され、将来のリスクを心配することなく、安全・確実・スピーディーに長屋を手放すことができます。精神的な負担をゼロにしたい方にとって、これ以上ない解決策だと私たちは考えています。
\ 無料で安心!まずは査定から /
今すぐあなたの物件をチェック
【FAQ】長屋の売却に関するよくある質問
最後に、これまでの解説で触れられなかった点や、特に多く寄せられるご質問について、Q&A形式でお答えします。
- Q1. 隣人に売却を知られずに進めることはできますか?
- Q2. 境界線が曖昧な場合はどうすればいいですか?
- Q3. 相続した長屋ですが、何から手をつければいいですか?
ここでは、お客様から特によくいただく3つの質問にお答えします。ご自身の状況と重なる質問もきっとあるはずです。ここまで読み進めていただいた中で生まれた、最後の小さな疑問や不安を、このセクションで解消していってください。
Q
1. 隣人に売却を知られずに進めることはできますか?
Q
2. 境界線が曖昧な場合はどうすればいいですか?
Q
3. 相続した長屋ですが、何から手をつければいいですか?
まとめ:隣人トラブルの不安は、専門家への相談で解消できます
この記事では、長屋売却における隣人トラブルの原因から、具体的な事例、そして円満に解決するためのステップまでを詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを5つにまとめます。
- 長屋には「共有部分」があり、これがトラブルの根本原因となる。
- 隣人との関係は、解体同意・内覧・売却後の3つのタイミングで特にこじれやすい。
- 承諾料の要求や売却後のクレームなど、金銭が絡む深刻なトラブルも現実に起きている。
- 個人で進める場合、現状把握と丁寧なコミュニケーションがトラブル回避の鍵となる。
- しかし、最も確実で心労がないのは、交渉やリスクを丸ごと任せられる専門の買取業者に依頼すること。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。長屋の売却は、法律や建物の知識だけでなく、複雑な人間関係も絡む難しい問題です。しかし、正しい知識と手順、そして何より「一人で抱え込まない」という意識があれば、必ず道は開けます。あなたの長年にわたるお悩みが、この記事をきっかけに少しでも軽くなることを心から願っています。
フィリアコーポレーションなら、隣人交渉もすべてお任せください
もしあなたが、この記事を読んで「自分一人で隣人と交渉し、売却を進めるのは難しい…」と少しでも感じたのであれば、ぜひ一度、私たちフィリアコーポレーションにご相談ください。
私たちは、単に不動産を買い取る会社ではありません。あなたの「悩み」や「不安」を、まるごと引き受ける会社です。
- 面倒な隣人交渉は、すべて私たちが代行します。
- 境界未確定、再建築不可の物件でも、現状のまま買い取ります。
- 売却後のクレームや責任は一切不要(契約不適合責任免責)です。
- 室内の残置物も、そのままで構いません。
相談したからといって、無理に売却をおすすめすることは決してありません。まずはあなたの状況を、私、越川に直接お聞かせください。秘密厳守で、あなたにとって最善の解決策をご提案することをお約束します。
下の無料査定フォームから、その重荷を私たちに預けてみませんか? あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

越川直之【宅地建物取引士】【空き家相談士】
代表ブログへ
株式会社フィリアコーポレーション代表取締役の越川直之です。
当社は空き家や再建築不可物件、共有持分など、一般的に売却が難しい不動産の買取・再販を専門とする不動産会社です。
これまでに1000件以上の相談実績があり、複雑な権利関係や法的・物理的制約のある物件にも柔軟に対応してきました。
弊社ホームページでは現場経験に基づいた情報を発信しています。
当社は地域社会の再生や日本の空き家問題の解決にも取り組んでおり、不動産を通じた社会貢献を目指しています。

