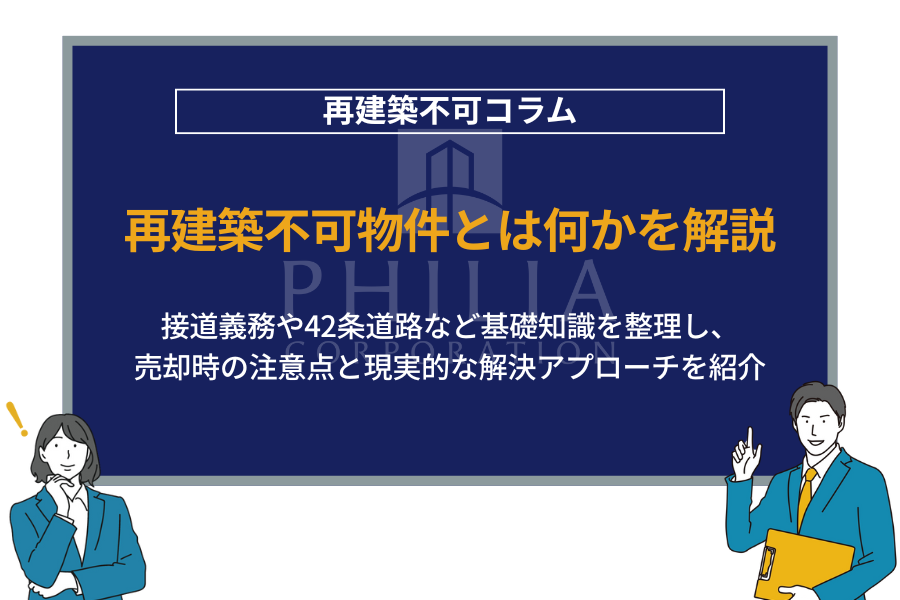コラム記事
連棟長屋の切り離し解体は可能?注意点とトラブル防止策
公開日 2025年9月3日
最終更新日 2026年1月19日

越川直之(宅地建物取引士 / 空き家相談士)
代表ブログへ訳アリ不動産1,000件以上の相談実績を持つ、空き家・再建築不可・長屋・共有持分の専門家。株式会社フィリアコーポレーション代表取締役。現場経験に基づき、訳アリ不動産売却の正しい知識を監修しています。
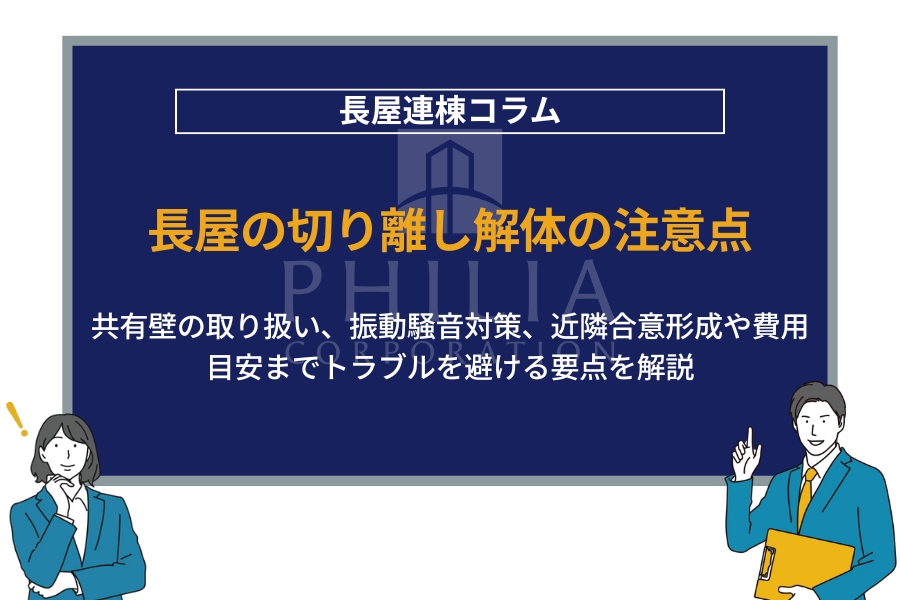
私たちはこれまで1000件以上の相談の中で、「連棟長屋を解体したいが、隣家と話がまとまらない」というお悩みに数多く向き合ってきました。長屋の解体は可能ですが、成功の鍵は「隣家との合意形成」にあります。この記事では、私たちの実務経験に基づき、トラブルを避けるための実践的な方法と、最終的な解決策までをお伝えします。
目次
結論:連棟長屋の切り離し解体は技術的に可能。ただし、超えるべきハードルがあります
この章では、連棟長屋の切り離し解体の可否について、以下の3つのポイントから解説します。
- なぜ「隣家の合意」が絶対条件なのか?建物の構造と法律上の理由
- 合意形成だけじゃない!解体前に確認すべき3つの法的チェックポイント
- 【要注意】解体できても「再建築不可」の土地になってしまうケースとは
「そもそも、うちの長屋は切り離して解体できるのか?」これは、所有者様が最初に抱く最大の疑問でしょう。結論から申し上げますと、現在の建築技術をもってすれば、ほとんどのケースで切り離し解体は可能です。しかし、それはあくまで「技術的に可能」という話に過ぎません。実際には、建物の構造や法律上の問題をクリアし、何よりも隣家の合意を得るという非常に高いハードルが存在するのです。安易にご自身の判断で計画を進めてしまうと、後戻りできない大きなトラブルに発展する危険性があります。
なぜ「隣家の合意」が絶対条件なのか?建物の構造と法律上の理由
隣家の合意が絶対条件である理由は、あなたの判断一つで隣家の資産価値や安全性に直接的な影響を与えてしまうためです。長屋は隣家と壁(界壁)を共有しているだけでなく、基礎や梁まで一体の構造になっていることが少なくありません。この状態で一方だけを解体すると、隣家の壁がむき出しになり雨漏りを引き起こしたり、建物の強度が低下し耐震性に深刻な問題が生じたりする恐れがあるのです。民法上も、共有資産の変更には共有者(この場合は隣人)の同意が必要と解釈されるため、法的な観点からも無断で進めることはできません。実際、同意なく解体を進めた結果、隣家から損害賠償や工事差し止めを求める訴訟に発展するケースは後を絶ちません。このように、切り離し解体は隣家との共同作業という側面を持つため、何よりもまず合意を得ることが絶対的な前提となります。
合意形成だけじゃない!解体前に確認すべき3つの法的チェックポイント
隣家の合意形成と並行して、ご自身の物件が法的にどのような状況にあるかを専門家と共に確認することが、後のトラブルを未然に防ぐ鍵です。見た目ではわからない法的な制約が隠れており、せっかく合意を得ても計画が頓挫したり、解体後に問題が発覚したりすることがあるためです。特に確認すべきポイントは以下の3つです。
- アスベスト(石綿)の有無:築年数の古い建物には、発がん性のあるアスベストが使用されている可能性があります。法律で事前調査が義務付けられており、もし含まれていた場合は特別な除去作業と追加費用が必要です。
- 境界の確定:長年のうちに境界標がなくなっているなど、隣地との境界が曖昧なケースは非常に多いです。解体前に境界を確定しておかないと、壁の補修やフェンスの設置などで必ずと言っていいほど揉める原因になります。
- 所有権・登記の確認:相続した物件の場合、登記名義が亡くなった方のままになっていることがあります。相続登記が未了のままでは、法律上ご自身の所有物と認められず、売却や解体といった処分行為ができません。
これらの調査は専門知識を要するため、解体業者や私どものような不動産会社に調査を依頼し、問題をクリアにしてから進めることが重要です。
【要注意】解体できても「再建築不可」の土地になってしまうケースとは
特に深刻なのが、解体後に新しい建物を建てられない「再建築不可」の土地になってしまうリスクです。建築基準法では、家を建てる敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接する」必要があります(接道義務)。古い長屋や連棟住宅には、この条件を満たしていない物件が少なくありません。例えば、敷地に面した道が建築基準法上の道路と認められていない「通路」だったり、道路に接している間口が2m未満だったりするケースです。現在は建物が存在していても、一度更地にしてしまうと二度と家を建てられなくなるのです。そうなれば土地の資産価値は著しく下がり、買い手を見つけることは絶望的になります。ご自身の土地が接道義務を満たしているかは、専門家でなければ判断が困難です。解体を決断する前に、必ず「再建築が可能か」を確認することが、将来の資産価値を守るためにも絶対に必要です。
\ 無料で安心!まずは査定から /
今すぐあなたの物件をチェック
トラブルを9割防ぐ!感情的な対立を避ける隣家との合意形成3ステップ
前の章で解説した通り、連棟長屋の解体は隣家の合意がなければ始まりません。この章では、最も重要かつ困難な「合意形成」を円満に進めるための具体的な3つのステップを解説します。
- 【ステップ1:交渉前】専門家と行うべき現地調査と「説明資料」の準備
- 【ステップ2:交渉時】誠意と配慮が伝わる話し方と将来的なメリットの提示
- 【ステップ3:合意後】約束事を明確に。「解体承諾書」の取り交わし
連棟長屋の解体交渉は、単なるお願いではありません。隣人にとっては、ご自身の生活や資産に直接関わる重大な問題です。だからこそ、感情的な対立を避け、論理的かつ誠実に話を進める必要があります。私たちフィリアコーポレーションが数々の現場で培ってきた経験から言えるのは、成功の鍵は「周到な準備」と「誠意ある対話」に尽きるということです。この3つのステップを丁寧に行うことで、交渉は格段にスムーズに進むはずです。
【ステップ1:交渉前】専門家と行うべき現地調査と「説明資料」の準備
交渉を円滑に進めるための第一歩は、専門家と共に現地調査を行い、客観的なデータに基づいた「説明資料」を準備することです。口頭だけの説明では、「本当に安全なのか」「うちの家に損害はないのか」といった隣人の不安を払拭できません。専門家による調査報告書や、工事計画書、補修計画といった具体的な資料を提示することで、計画が安全性を十分に考慮したものであることを論理的に示すことができます。説明資料には、主に「①解体工事の手順書」「②騒音・振動対策の具体策」「③解体後の隣家の壁の補修方法と図面」「④緊急時の連絡体制」などを盛り込みます。特に壁の補修方法は、隣人の最大の懸念事項です。どのような材料で、どのように施工するのかを具体的に示すことで、安心感に繋がります。手ぶらで交渉に臨むのではなく、専門家のお墨付きを得た客観的な資料を準備することが、合意形成の土台となるのです。
【ステップ2:交渉時】誠意と配慮が伝わる話し方と将来的なメリットの提示
準備した資料を手に隣家へ説明に伺う際は、何よりもまず「ご迷惑をおかけします」という謙虚な姿勢と、相手への配慮が重要です。解体工事は、どれだけ対策をしても騒音や振動で少なからず負担を強います。その点を真摯に詫び、理解を求める姿勢がなければ、相手も感情的になりかねません。こちらの都合だけを押し付けず、相手の懸念や質問に丁寧に耳を傾けることが信頼関係を築きます。その上で、解体による隣家への「将来的なメリット」を伝えることも有効です。例えば、「老朽化した建物がなくなることで、倒壊や火災のリスクが減り、お宅の安全性も高まります」「日当たりや風通しが改善される可能性もあります」といった具合です。一方的な「お願い」ではなく、相手の立場を尊重し、誠意ある対話を心がけること。これが、難しい交渉を「円満な合意」へと導く鍵となります。
【ステップ3:合意後】約束事を明確に。「解体承諾書」の取り交わし
口頭で合意が得られたら、必ずその内容を文書化した「解体承諾書」を取り交わし、お互いに保管しておくことが、後のトラブルを防ぐために不可欠です。口約束だけでは、「言った・言わない」の水掛け論になるリスクが非常に高いからです。承諾書は、あなた自身を守るだけでなく、隣人にとっても「約束が守られる」という安心材料になります。承諾書に決まった形式はありませんが、最低でも「①工事の概要と期間」「②施工業者」「③壁の補修方法や費用負担について」「④万が一、隣家へ損害を与えた場合の補償について」「⑤署名・捺印と日付」は明記すべきです。このような書面をきっちり作成する姿勢を見せることで、あなたの誠実さが伝わり、隣人の信頼もより一層深まります。気持ちよく合意に至ったとしても、必ず書面で約束事を明確にすること。これが円満な関係を最後まで維持するための最後の砦となります。
\ 無料で安心!まずは査定から /
今すぐあなたの物件をチェック
想定外の出費を防ぐ。切り離し解体の費用と工事の注意点を解説
隣家の合意が得られたら、次はいよいよ具体的な工事の準備です。しかし、ここでも思わぬ落とし穴が潜んでいます。この章では、費用面と工事における注意点を解説します。
- 通常の解体と何が違う?費用の内訳と高くなりやすいポイント
- 騒音・振動だけではない!工事中・工事後に発生しうる隣家とのトラブル事例
- もし同意が得られなかったら…?その場合の2つの現実的な対処法
連棟長屋の解体費用は、一般的な戸建て住宅に比べて割高になる傾向があります。それは、隣家に影響を与えないよう、より慎重で繊細な手作業が必要になるためです。また、費用をかけて解体したのに、後からトラブルが発生しては元も子もありません。事前にリスクを把握し、対策を講じておくことが、安心して工事を終えるために重要です。ここでは、具体的な費用の話から、万が一同意が得られなかった場合の対処法まで、踏み込んで解説します。
通常の解体と何が違う?費用の内訳と高くなりやすいポイント
連棟長屋の解体費用は、坪単価3〜5万円程度が相場ですが、通常の解体に加え「切り離し工事」や「壁の補修費用」が別途発生するため、総額では高くなるのが一般的です。重機を大胆に使うことができず、隣家を傷つけないよう手作業で慎重に壊す部分が多くなるためです。また、解体後に隣家の壁がむき出しになるため、防水処理や外壁材の設置といった補修工事が必須となり、この費用も上乗せされます。費用が高くなりやすい他の要因としては、前面道路が狭く重機やトラックが入れない場合の人件費増加や、アスベスト除去費用、地中から予期せぬ障害物が出てきた場合の撤去費用などが挙げられます。このように、連棟長屋の解体は追加費用が発生しやすいため、複数の業者から見積もりを取り、どこまでの工事が含まれているのかを詳細に確認することが、想定外の出費を防ぐためには不可欠です。
騒音・振動だけではない!工事中・工事後に発生しうる隣家とのトラブル事例
事前に合意を得ていても、工事中や工事後に予期せぬトラブルが発生し、隣家との関係が悪化するケースは残念ながら少なくありません。工事はあくまで「他人の敷地」で行われるものであり、隣人は常に不安やストレスに晒されているからです。少しの油断や配慮不足が、不信感を招きかねません。よくあるトラブル事例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 粉塵・ゴミの飛散:養生が不十分で、隣家の洗濯物や車を汚してしまった。
- 職人のマナー違反:休憩中に隣家の前で喫煙や大声で雑談をし、不快感を与えた。
- 補修壁の仕上がり不満:事前の説明と違う、色が気に入らないなど、壁の完成後にクレームが入った。
- ひび割れなどの実害:解体工事の振動で、隣家の内壁にひびが入った、窓の建付けが悪くなった。
このようなトラブルを防ぐには、信頼できる誠実な工事業者を選ぶことが何よりも重要です。価格だけでなく、近隣への配慮や万が一の事故に備えた保険加入の有無などを確認し、安心して任せられるパートナーを見つけましょう。
もし同意が得られなかったら…?その場合の2つの現実的な対処法
どれだけ誠実に交渉を重ねても、様々な事情から隣家の同意が得られない場合、解体を強行することはできません。その際の現実的な対処法は「専門家による代理交渉」と「買取」の2つです。当事者同士では感情的になり話が進まなくても、第三者である専門家が間に入ることで、相手も冷静に話を聞く姿勢になることがあります。それでも解体が不可能であれば、問題のある不動産をそのまま手放す、という選択肢を検討する必要があります。
- 専門家による代理交渉:弁護士や、私たちフィリアコーポレーションのような不動産のプロが、あなたに代わって隣家と交渉します。
- 現状のまま買取を依頼する:交渉の労力や解体費用、トラブルのリスクを一切負いたくない場合の最終手段です。隣家との交渉が難航しているような複雑な状況の不動産でも、専門の買取会社であれば、現状のまま買い取ることが可能です。
同意が得られず八方塞がりだと感じた時こそ、一人で抱え込まないでください。
こちらご相談いただければ、交渉から買取までワンストップで最適なご提案をいたします。
\ 無料で安心!まずは査定から /
今すぐあなたの物件をチェック
【実例】交渉・解体が困難な連棟長屋を「買取」で解決した2つのケース
言葉で説明されても、なかなかイメージが湧きにくいかもしれません。そこで、私たちフィリアコーポレーションが実際に取り扱い、売主様の悩みを「買取」という形で解決した2つの具体的なケースをご紹介します。
- ケース1:隣家との関係が悪化していた川崎市の長屋を「交渉ごと丸投げ」で弊社が買取
- ケース2:相続人全員が遠方に住む川口市の長屋を「残置物ごと」弊社が買取
「解体もできず、売ることもできない…」そんな八方塞がりの状況でも、解決策は必ずあります。これからご紹介するのは、机上の空論ではない、私たちが実際に経験したリアルな事例です。売主様がどのような点に悩み、そして私たちがどのようにその問題を「買取」によって解決したのか。ご自身の状況と照らし合わせながらご覧いただくことで、きっと新たな活路を見出していただけるはずです。
ケース1:隣家との関係が悪化していた川崎市の長屋を「交渉ごと丸投げ」で弊社が買取
ご相談者様は、長年空き家だった長屋の解体を試みたものの、隣家との関係が悪く交渉が一切進まない状況で、最終的に弊社が「交渉ごと丸投げ」で買い取らせていただきました。
【ご相談内容】川崎市に長屋を所有するA様は、建物の老朽化が激しく、行政からも管理に関する指導を受けていました。しかし、隣家とは先代からの付き合いで関係がこじれており、A様が解体の話を持ち掛けても聞く耳を持ってもらえず、完全に途方に暮れていらっしゃいました。
【弊社の解決策】弊社にご相談いただき、建物の状況と根深い隣家との関係性を踏まえ、「これ以上ご自身で交渉を進めるのは精神的なご負担が大きすぎる」と判断。そこで、隣家との今後の交渉も含めて、現状のまま弊社が買い取るというご提案をしました。A様は「本当にこの状態で買い取ってもらえるのか」と驚かれていましたが、査定額にもご納得いただき、ご契約いただきました。結果、A様は最も頭を悩ませていた隣家との交渉から一切解放され、不動産を現金化することに成功されました。
ケース2:相続人全員が遠方に住む川口市の長屋を「残置物ごと」弊社が買取
相続人の皆様が遠方にお住まいで、管理もままならなかった川口市の長屋を、室内に家財が残った「残置物ごと」の状態で弊社が買い取らせていただいた事例です。【ご相談内容】ご兄弟で川口市にあるご実家の長屋を相続されたB様。しかし、相続人全員が県外にお住まいで、現地に足を運ぶことすら困難な状況でした。室内には亡き親御様の家財道具が大量に残っており、片付けだけでも大変な労力と費用がかかるため、途方に暮れておられました。【弊社の解決策】B様からのご相談に対し、弊社は「現地への立ち会いは一切不要です」とお伝えし、オンラインと郵送で手続きを進行。最大の懸念事項であった室内の残置物についても、「一切片付けていただかなくて結構です。そのままの状態で買い取ります」とご提案しました。もちろん、隣家へのご挨拶や今後の話し合いもすべて弊社が引き継ぎます。B様からは「手間も費用も全くかからず、肩の荷が下りた」と大変お喜びいただけました。
連棟長屋の解体・売却に関するよくある3つの質問
最後に、これまでの解説で触れられなかった点や、お客様から特によくいただくご質問について、Q&A形式でお答えします。
- Q1.解体後の壁の補修費用は、どちらが負担するのが一般的ですか?
- Q2.遠方に住んでおり現地に行けないのですが、相談や買取は可能ですか?
- Q3.解体後の更地を売却することも含めて相談できますか?
連棟長屋の解体や売却は、ケースバイケースの部分が多く、個別の状況によって様々な疑問が湧いてくるものです。ここでは、特に多くの方が疑問に思われる3つのポイントに絞って解説します。ご自身の状況に当てはまるものがあれば、ぜひ参考にしてください。もし、ここにない疑問や、より詳しい話を聞きたい場合は、いつでもお気軽にご相談いただければと思います。
Q
1.解体後の壁の補修費用は、どちらが負担するのが一般的ですか?
Q
2.遠方に住んでおり現地に行けないのですが、相談や買取は可能ですか?
Q
3.解体後の更地を売却することも含めて相談できますか?
まとめ
連棟長屋の切り離し解体について解説してきましたが、最後に重要なポイントを5つにまとめます。
- 解体は可能だが隣家の合意が絶対条件:技術的に可能でも、隣家の合意なくしては一歩も進めません。
- 交渉の鍵は事前準備と誠意:専門家と作成した資料を基に、誠意をもって対話することが円満合意への道です。
- 費用は割高と心得る:通常の解体に加え、壁の補修費用なども発生するため、余裕を持った資金計画が必要です。
- 解体前の「再建築不可」チェックは必須:解体後に資産価値が暴落するリスクを防ぐため、必ず専門家に事前確認を依頼しましょう。
- 最終手段は「買取」:交渉や解体が困難な場合、専門の買取会社に現状のまま売却する、という有効な解決策があります。
連棟長屋の問題は、法律、建築、そして人間関係が複雑に絡み合う、非常にデリケートな問題です。だからこそ、決して一人で抱え込まず、専門家の知見を頼ることが、トラブルなく円満に解決するための最も確実な近道と言えます。
連棟長屋の問題、一人で抱え込まずに無料相談からはじめませんか?
この記事を読んで、「うちのケースはどうなんだろう」「専門家の意見を聞いてみたい」と思われたなら、ぜひ一度私たちフィリアコーポレーションにご相談ください。
私たちは、これまで1000件以上の訳あり不動産の問題を解決してきた専門家集団です。ご相談いただいたからといって、無理な営業は一切いたしません。まずはあなたの状況をじっくりお聞かせいただき、解体、売却、そして買取という選択肢の中から、あなたにとっての最善の解決策を一緒に考えさせていただきます。査定もご相談も無料、もちろん秘密は厳守いたします。そのお悩み、私たちにお聞かせください。解決への第一歩を、ここから踏み出しましょう。

越川直之(宅地建物取引士 / 空き家相談士)
代表ブログへ
株式会社フィリアコーポレーション代表取締役の越川直之です。
当社は空き家や再建築不可物件、共有持分など、一般的に売却が難しい不動産の買取・再販を専門とする不動産会社です。
これまでに1000件以上の相談実績があり、複雑な権利関係や法的・物理的制約のある物件にも柔軟に対応してきました。
弊社ホームページでは現場経験に基づいた情報を発信しています。
当社は地域社会の再生や日本の空き家問題の解決にも取り組んでおり、不動産を通じた社会貢献を目指しています。